「名は体を表す」ということわざを聞いたことがありますよね?
物事の名前には、その本質が表されています。
世の中の商品を見渡しても、名前を変えて大ヒットした商品がありますし、
子供の名前で漢字を決める時なんかはかなり時間を使って考えます。
それだけ名前とは重要なもの。
子供が産まれて初めて皆さんに与えられる名前があります。
それは・・・・「親」という文字です。
実はこの文字には、
子育てをする上で非常に重要な本質が隠されていたのです。
ここで、少しクイズを出したいと思います。
この「親」という文字は3つの漢字に分解できるのですが、
何だと思いますか?
頭の体操だと思って少し考えて下さい。
自分なりの答えが出てから、読み進めて下さい。
分かりましたでしょうか?
では、答え合わせです。
「親」=「木」+「立」+「見」となります。
これを文章として繋げると
「親は木に立って子供を見守るもの」です。
これはすなわち、
あまり子供のすることには手出しはせずに、見守る姿勢でいましょう。
このように捉えることが出来ると思います。
少子化が加速する中で、
出来るだけ我が子には幸せになって欲しい。
きちんと身の回りのことは出来るようにしないと、
食事のマナー、文字のおけいこ、習い事・・・・親が考える「良いこと」を子供にさせます。
その気持ちは、親として痛いほど理解できます。
ですが、少し立ち止まって欲しいのです。
子供は大人と違って、物事をこなすスピードも違いますし、
経験も違います。
親が思うように取り組めなくて当然と考えましょう。
○○するべきではなく、
○○できたら嬉しいな、くらいの気持ちです。
親というのは、基本的に子供を遠くから見守る存在でいいと思います。
1、2歳頃は何でもかんでも親が手を貸す必要がありますが、子供が何でもやりたいと言ったら、
失敗することを前提として任せてみるのです。
この「失敗することを前提に」という考え方は、
非常に重要です。
なぜなら、大人の私たちは経験もあって理解できますが、子供にとっては
何が失敗かは経験してみないと分かりません。
例えば、
コップにお茶を入れたいといって、やかんからお茶を注ごうとします。
やかん+お茶なので、子供にとっては重たい。
親はかなり高い確率でこぼすだろうと思って、
子供が嫌がるのに、先回りしてやかんを持ちます。
その結果、きちんと注ぐことが出来ました。
親にとっては良かったのですが、子供にとっては消化不良です。
自分で全部やりたいと言ったのにさせてもらえないのは、
子供の成長や意欲に繋がりません。
この場合は、とりあえず子供の言うとおりに全て任せてみるのです。
そのことでお茶をこぼす可能性は高くなるかも知れませんが、
子供にとっては、こぼすということも大事な経験の一つ。
お茶をこぼさせたくない(掃除が大変だ)から、手を貸したのであって、
子供に失敗させたくないからではありませんよね?
こぼすかも知れないからとあたふたするのではなく、
こぼす前提で構えていると、そうなったとしても不思議と穏やかに対応できるものです。
(そうなる前提で、事前にタオル等を準備しておくのが良いです)
私も子育てについて学ぶまでは、
こぼすことに対してイライラしていた時期がありました。
学んでからは、それがかなり減ったと思います。
子供は成功、失敗も含めて全てが経験。
親が何でも先回りせずに、
子供がやりたいと言ったら任せてみましょう。
もちろん命に関わるようなことは、
すぐに手を差し伸べる準備が必要です。
子供たちといろいろな公園に行っていますが、
その中でも特に好きなのは、見晴らしの良いところ。
遠くからでも、子供の様子を見ることが出来るからです。
その公園では私がほとんど介入することなく、
子供は勝手に遊んでいます。
時々、一緒にすべり台をやろうと声をかけてくれるので、
そのような場合のみ一緒に遊びます。
こういう事が子育てなのかなぁと個人的に思います。
(子供がこちらに声をかけるまでは見守るということ)
子供は、環境さえ与えれば自主的に何でもやろうとするのです。
その対極にあるのが「ヘリコプターペアレント」という言葉。
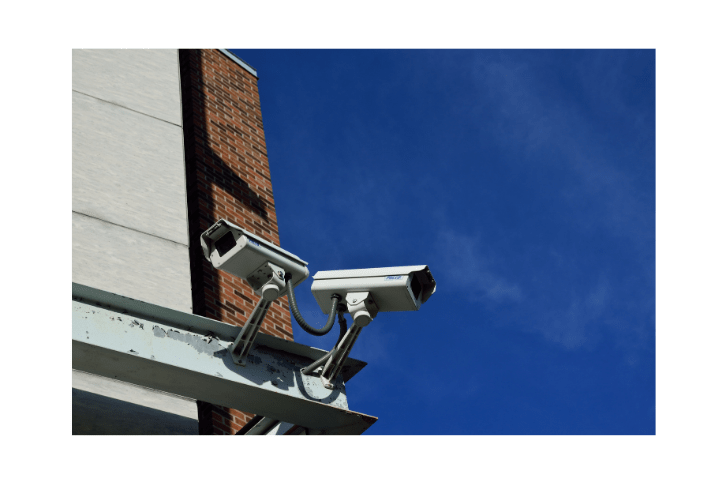
これは、親が子供の上をヘリコプターのように張り付いて監視することです。
過保護・過干渉の親である表現として用いられています。
このように育てられた子供は親の態度を気にするあまり、
自主性がなく指示待ち人間になる、自分の意見を持たないようになってしまいます。
子供は親の所有物ではなく、独立した個人として生きなければなりません。
子育ての目的は子供の自立にありますが、
言い換えると「生きる力」をつけることです。
常に監視&干渉されていれば、
この力をつけることは出来ないでしょう。
親として子育てにどっぷりつかるのは、
せいぜい小学生くらいまでだと思います。
それ以降はだんだんと親の手を離れ、
自立に向けて活動をしていきます。
答えの用意された世界から、
正解の無い世界へと巣立っていく我が子。
子供の自立の芽を、親が潰してしまうということが無いように、
出来ることから見守る子育てを実践して下さいね。



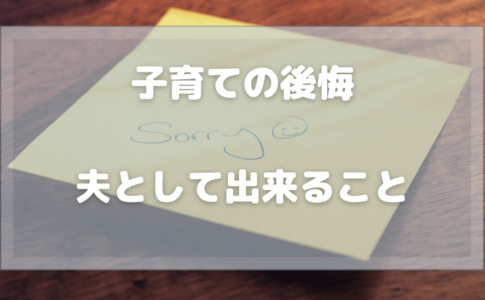

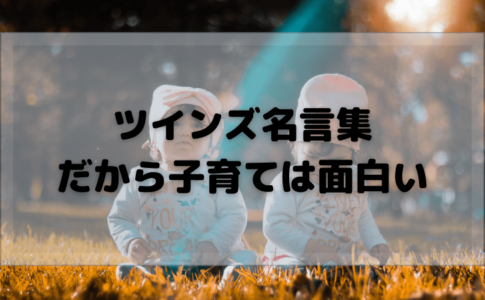
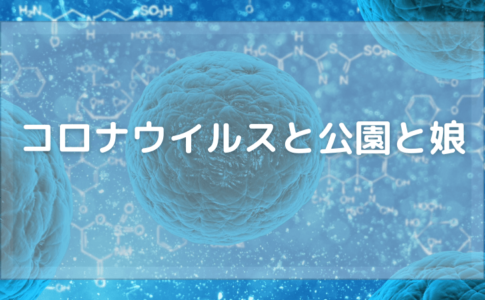
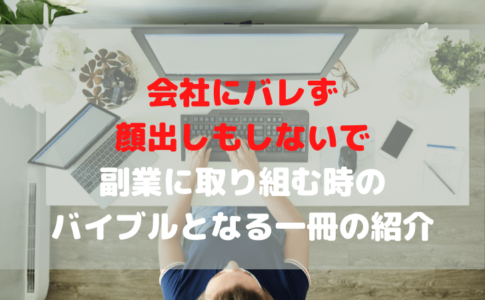
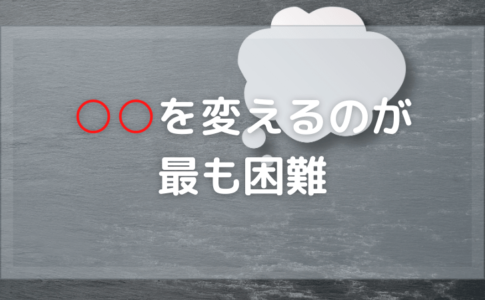

コメントを残す