あなたのお子さんは挨拶をする子供でしょうか?
我が家の5歳の娘たちは、
いつもする訳ではありませんが、比較的良くする方だと思います。
挨拶って、人の反応(性格)を知れる面白い手段ですよ。
あなたの職場を思い浮かべてください。
挨拶をきちんとする人は、話しかけられやすいし、相談しやすい雰囲気がありますよね?
明るくハキハキ言う人もいれば、ぶっきらぼうな人もいる。
ベテランになるほど、あまりしなかったり声が小さかったりしますが、
新人の頃は仕事は出来なくても、挨拶の声だけは大きかったですよね。
仕事における期限を守るのと同じくらい、重要なものだと感じています。
もしあなたの子供が挨拶をあまりしないなぁと感じていたら、
先に結論を言います。
親がもっと積極的に挨拶をする習慣をつければ、
自然と行うようになります。
なぜなら、子供は親の姿や仕草を良く見ているからです。
そのように感じたエピソードを1つ紹介したいと思います。
我が家は1年ちょっと前に引っ越しをしました。
後から分かったことなのですが、
住んでいる家の前がちょうど小学校の通学路になっており、
毎日多くの小学生が前を通っています。
賑やかだし、
ああいう若いエネルギーというのは、周りを活性化させますね。
気分が乗らない朝でも、挨拶をするだけで気持ちが上向きます。
彼・彼女たちとの交流は引っ越しをした頃はありませんでした。
子供たちが自転車の練習(朝練)をするようになり、
(通学路とはいえ、車も通ることがあるから目を離してはいけないと思い、しぶしぶ)
外に出たことをきっかけに、交流を持つようになりました(笑)
最初は、自転車に乗る子供たちを見守るだけで、
家の前を通る子供たちには何の声かけ(挨拶)もしていませんでした。
あちらからの挨拶も、当然ながら一切無しです。
通学路には学校の先生が所々に立っており、
先生が挨拶をすると、皆もしていました。
ここで「挨拶」という言葉の由来を調べてみると、
どうやら禅宗の「一挨一拶(いちあいいっさつ)」からきているそうです。
「挨拶」の「挨」は、押す、近づくなどの意味があります。
「拶」は、迫るという意味なのだそうです。
どちらも似たような意味だなあと思いませんか?
一挨一拶の意味は、師匠が弟子に言葉を投げかけ、
その返答で力量をはかるようにしていたようです。
それが、現代では最初のコミュニケーションの言葉として広く用いられています。
私なりの解釈を加えると、挨拶というのは、
「最初に心を開く手段」
だと思います。
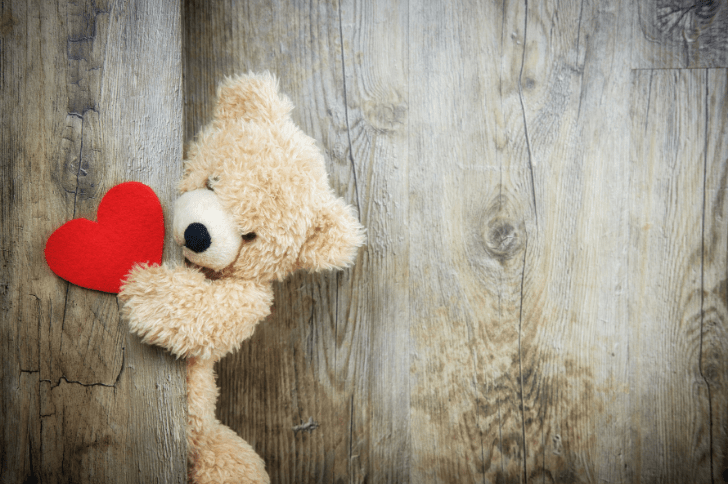
「近づく」「迫る」などの意味がありますから、
物理的・精神的な距離を縮めるものだと思うからです。
ですから、
やるなら自分から先に言う方が良いと思います。
(自分から心を開くという意味になるからです)
もし、挨拶をしても無視をされたなら、
それは距離が縮まっていないということ。
私の前を無言で通る子供たち、
会社では知らない人とすれ違う時でも挨拶くらいはします。
自分も、教育や子育てを学んで実践している身としては、
何も言わないのも何だかもやもやします。
そして、
あるとき思い切って「おはよう」と挨拶をするようにしました。
最初のうちは、ほとんどの子供が挨拶をしませんでした。
それは当然の反応。
今まで挨拶をして来なかったおじさん(とはいっても、まだ30代半ばです)が、
突然おはようと言い出したのですから。
子供たちからすれば、
「この人は何で急に挨拶をし始めたのか」と疑問に思うのも無理はありません。
挨拶を返してくれるのは全体の1割くらいだったと思います(笑)
初日はそんなものだと割り切っていました。
それから自転車の練習がある日(ほぼ毎日)は、挨拶を行うようになりました。
だんだんと繰り返して行くうちに、
今では7割くらいはしてくれるようになりました。
私から言わなくても、向こうから挨拶をしてくれる子もいます。
(そのよう子は、育ちがいいなぁと勝手に思います)
何でもそうですが、
まずはこちらが心を開かないと、相手も開いてくれませんよね。
そんなある時ツインズの次女が
「お父さんと一緒に挨拶をしたい」と言いました。
どうしてと尋ねると、
今までは恥ずかしかったから挨拶をしていなかった。
でも、一緒なら出来るとのことです。
その日は、気持ちよく2人で挨拶をすることが出来ました。
挨拶をしない子供に口うるさくしなさいと言うのではなく、
親が行動を示すことで、子供は真似をしたくなるのです。
悪い言葉を使えば子供も使うし、
親の習慣がそのまま子供にも影響を与えます。
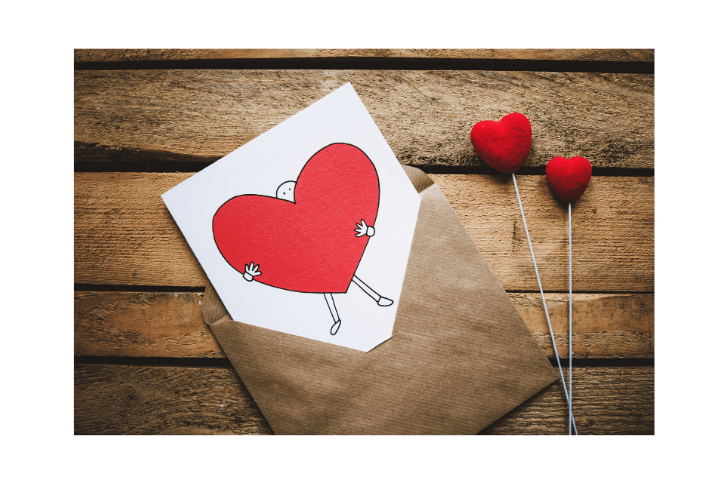
挨拶をする子供もやり方はそれぞれあって、
きちんと目を見て大きな声で言う子もいれば、
小さい声や目を合わせない子もいます。
全くしない子は、
性格的なものなのか、年頃で恥ずかしいからなのか、
今日は気分が乗らないからなのかは分かりません。
家庭であまりそのような習慣がないことも考えられます。
そういう子を見る度に、
子供なのに元気がないなぁと、おせっかいな親心が湧いてしまいます。
思春期が来て、
挨拶を面倒くさがる年頃になったとしても、
親から子供に真っ先に挨拶をするように心がけてください。
例え、子供がしなくても。
言葉で説明しなくても、いずれ重要性が理解できる時が来ますので。
いずれは9割9分の子がしてくれるように、
これからも挨拶をしていこうと思います。
ぜひ、あなたも積極的にする習慣をつけて下さいね。
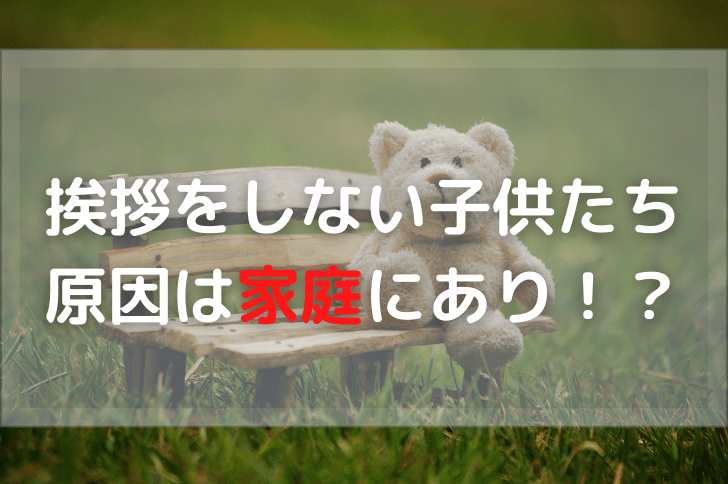
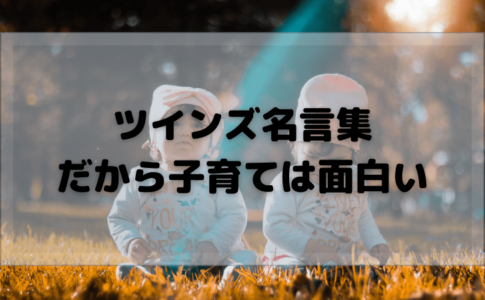
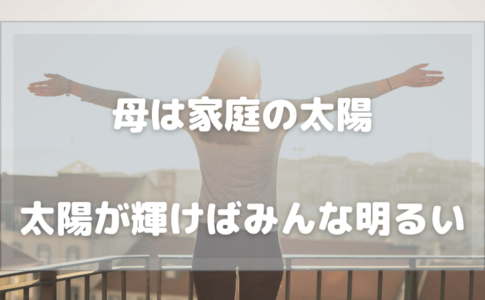

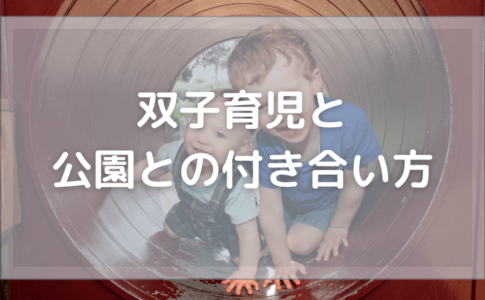
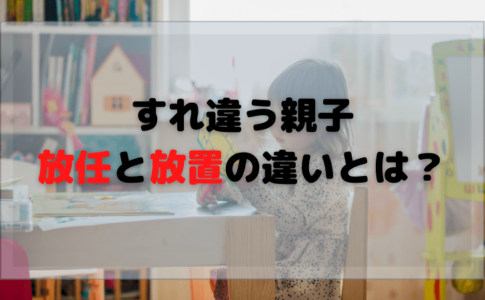
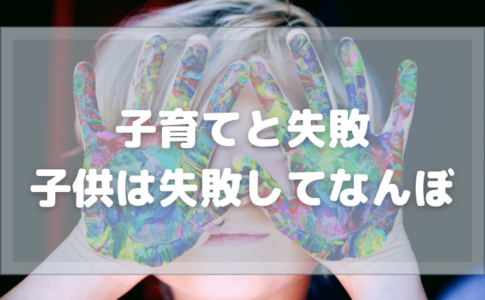



コメントを残す